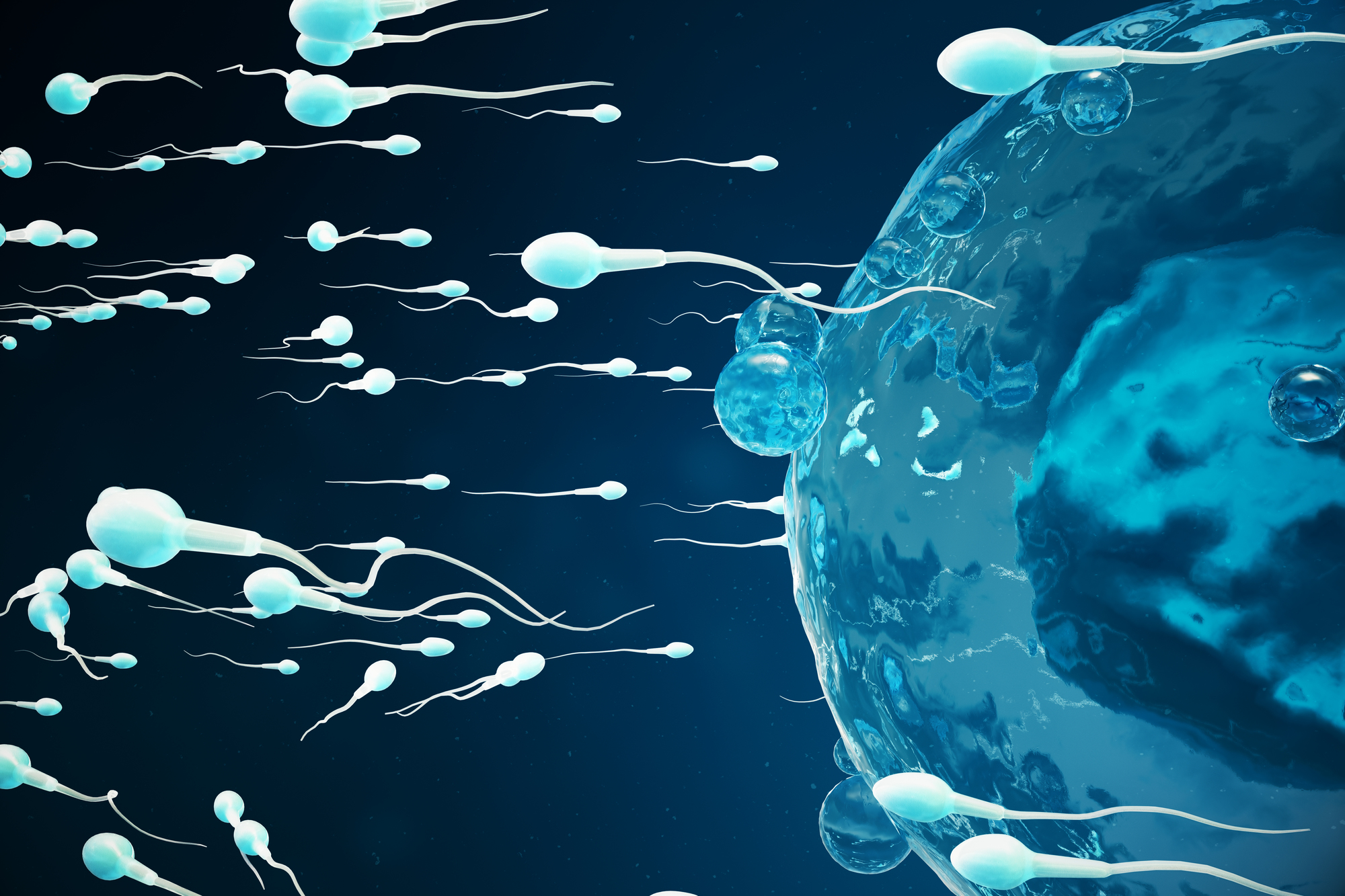一般不妊治療
更新日:
不妊治療の保険適用はどこまで?適用範囲と注意点を解説

以前は基本的に自費診療だった不妊治療ですが、2022年4月より健康保険が適用されるようになり、今までよりも利用しやすくなりました。しかし、すべての不妊治療が保険適用となるわけではありません。また、かえって負担が増えてしまうケースもあることに注意が必要です。
本記事では、不妊治療には保険がどこまで使えるのか、不妊治療の保険適用範囲と注意しておくべき点について解説します。
ページコンテンツ
2022年4月から不妊治療の保険適用範囲が拡大不妊治療の保険適用の対象となる年齢と回数不妊治療の保険適用によるメリット不妊治療の保険適用による注意点地方自治体独自の不妊治療の助成金制度も活用可能保険適用の不妊治療を知って早めに不妊治療を始めよう2022年4月から不妊治療の保険適用範囲が拡大
2022年4月から、不妊治療の保険適用範囲が拡大しています。その背景には、少子化対策が喫緊の課題となっていることが挙げられます。
少子高齢化を解決するには、なんといっても子供を増やすことが先決です。とはいえ、子供が欲しくても産めない場合や、仕事と不妊治療の両立が難しい場合など、さまざまな問題が関係しています。その中のひとつに、費用の問題も大きくのしかかっていました。
不妊治療は、以前は100%自費診療だったため、非常に高額な費用がかかっていました。また、いつまで続くかわからない不妊治療は、当事者にとって身体的・心理的負担も相当大きいものです。
そのほかにも、保険適用になることによって不妊治療にかかるデータを蓄積でき、不妊治療の質の標準化が図れるという観点がありました。
さらに、今はまだ不妊治療を理由に仕事を休みづらい雰囲気がありますが、不妊治療が保険適用となることで「不妊自体を病気として捉え、治療の対象である」という社会的な理解が広がる期待もあります。
これらの背景から、不妊治療にかかる費用に広く医療保険の適用を検討することとなったのです。
不妊治療前検査の保険適用は従来どおり
不妊の原因を探るための検査は、保険適用のままです。
不妊の原因は、「男性不妊」「女性不妊」「原因のわからない不妊」の3つに大別できますが、それらを判断するために、不妊治療を希望される全ての患者さまに初期検査を実施しています。
にしたんARTクリニックでは、女性向けは「スクリーニング検査」、男性向けには「男性検査」と呼び方を分けています。
スクリーニング検査を行う際の費用は保険適用で7,260円、自費診療の場合29,150円となります。男性検査は自費診療のみで11,000 円となっています。ただし、他のクリニックなどで受けた検査結果の期限が有効な場合、検査を省略できることもあります。
初期検査の内容は下記のとおりです。
診察所見
女性については、内診で超音波のプローブと呼ばれる細長い器具を腟に挿入し、子宮や腟の状態を観察します。また、性交後に女性の子宮頸管粘液を採取して精子が腟内に入り込めているかどうかを確認するヒューナー(性交後)検査も行うことも可能です。
精子の所見
男性の精液を採取し、精子の量や濃度、運動率、形状などを観察する精液検査を行います。
画像検査
X線を使用した卵管造影検査で、卵子と精子が出会う場所である卵管が狭くなったり、周りの組織と癒着したりしていないかどうかを確認します。
血液検査
採血を行い、女性側は黄体化ホルモンや卵胞刺激ホルモン、プロラクチン(乳汁分泌ホルモン)、エストロゲン(卵胞ホルモン)を測定します。男性側も採血をして、男性ホルモンや性腺刺激ホルモンの測定を行います。
2022年4月に保険適用になった治療
不妊治療の保険適用範囲が拡大したことで新たに保険適用になったのは、下記の治療です。ただし、治療費以外に別途、諸費用がかかる場合があります。
タイミング指導(タイミング法)
タイミング指導とは、医師が女性の排卵期から妊娠しやすい日を予測して、性交のタイミングを指導する治療です。費用の目安は、検査内容により多少変動はあるものの、1周期あたり数千円~20,000円程度です。
人工授精(AIH)
人工授精(AIH)とは、医師が女性の排卵期から妊娠しやすいであろうと予測した日に、男性の精液から採取した精子を女性の子宮にカテーテルを使って注入する治療です。1回あたりの費用の目安は、保険診療では5,000円程度、自費診療では20,000~30,000円程度です。
体外受精(IVF/ふりかけ法)
体外受精(IVF)とは、女性の子宮から採取した卵子をシャーレに入れ、男性から採取した精液から活発な精子を選定し、卵子にふりかけて自力で受精を促す治療です。1回あたりの費用の目安は、保険診療では12,000円程度、自費診療では90,000~100,000円程度です。
顕微授精(ICSI)
顕微授精とは、体外受精で受精できなかった場合に、細いガラスの管を使って女性から得た卵子に男性から得た精子を1匹注入して受精させた上で、女性の子宮に戻す治療です。1回あたりの費用の目安は戻す卵子の個数にもよりますが、保険診療では15,000~40,000円程度、自費診療では70,000~190,000円程度です。
採卵
採卵は、経腟超音波のプローブの先に女性の腟から卵巣に向かって針を刺し、卵胞液ごと吸引して卵子を得ることを指します。採卵の費用の目安は個数にもよりますが、保険診療では10,000~30,000円程度で別途麻酔の料金がかかります。自費診療は使用する麻酔の種類によって、30,000~200,000円と幅があります(別途、諸費用がかかります)。
受精卵・胚の培養
体外受精や顕微授精などで受精が成立した受精卵は、培養器に入れて胚になるまで培養します。費用は、受精卵の個数にもよりますが、保険診療の場合10,000~30,000円程度、自費診療の場合50,000~130,000円程度です。また、初期培養から追加培養が発生したときは、上記金額に保険診療の場合は4,500~9,000円程度、自費診療の場合は30,000~70,000円程度上乗せされます。
胚凍結
受精卵を胚にしたものを凍結して、次の月経周期での移植に向けて保存する場合があります。その場合は、凍結保存管理料がかかります。保険診療の場合は個数にもよりますが、費用の目安は15,000~40,000円程度、自費診療の場合は20,000~130,000円程度です。1年以上保存する場合は、更新料として保険診療の場合は10,000円程度、自費診療の場合は50,000円程度かかります。
胚移植
胚移植とは、受精卵を培養して胚になったものを女性の子宮にカテーテルで戻す治療です。1回の周期のうちに胚を移植する新鮮胚移植の場合、費用の目安は、保険診療で20,000円程度、自費診療で50,000~100,000円程度かかります。凍結した胚を融解して移植する凍結胚移植の場合は、保険診療では40,000円程度、自費診療では70,000~130,000円程度かかります。
胚移植について詳しくは、こちらのページをご覧ください。胚移植とは?
不妊治療の保険適用の対象となる年齢と回数

一般不妊治療のタイミング指導(タイミング法)や人工授精(AIH)には年齢・回数制限はありません。ただし、生殖補助医療(ART)には年齢制限と回数制限があります。
年齢制限は、治療開始時の女性の年齢が43歳未満となります。回数については、初めて治療を開始する際の女性の年齢が40歳未満の場合は移植の回数が1子ごとに通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は移植の回数が1子ごとに通算3回までという制限が設けられています。
42歳で不妊治療を開始して治療期間中に43歳になった場合は、その周期の胚移植までが保険適用です。この回数は出産ごとにリセットされます。
なお、タイミング法や人工授精には年齢制限や回数制限はありません。
生殖補助医療(ART)の保険適用対象者の条件
| 初めての治療開始時の女性の年齢 | 回数上限 |
| 40歳未満 | 通算6回まで(1子ごと) |
| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごと) |
不妊治療の保険適用によるメリット
不妊治療が保険適用になったことによるメリットは、主に3つ挙げられます。詳しい内容は下記のとおりです。
経済的な負担が軽減される
不妊治療が保険適用になる大きなメリットは、費用負担が3割となり、経済的な負担が軽減されることです。特に、生殖補助医療(ART)といわれる体外受精や顕微授精(ICSI)にステップアップしようとしても費用が高額であきらめていた人も、チャレンジしやすくなりました。
また、診療報酬は決められているので、北海道から沖縄までどのクリニックで不妊治療を受けても同じ金額で治療を受けられるようになりました。
高額療養費制度の対象になる
高額療養費制度とは、ひと月に支払う医療費が一定の金額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
高度療養費制度は保険適用の治療のみが対象なので、これまで自費診療だった不妊治療は適用対象外でした。しかし、2022年4月の保険適用拡大で、不妊治療についても高額療養費制度の対象となりました。
不妊治療の方法や進め方が明確になる
不妊治療の保険適用範囲が拡大されたことで、年齢や回数の制限はあるものの、ある程度は不妊治療の標準化ができるようになりました。不妊治療が自費診療だったときは、個々に合わせたオーダーメイドの治療になっていましたが、標準化されたことで不妊治療の内容やステップがよりわかりやすくなったというメリットもあります。
不妊治療の保険適用による注意点

良いことしかないように見える不妊治療の保険適用ですが、注意点があります。どのようなことに気をつければいいのか、詳しく見ていきましょう。
保険診療と自由診療の併用は認定施設なら可能なケースも
現行の法律(健康保険法)では、先進医療と一般不妊治療の併用はできるものの、保険診療と自費診療の併用は基本的には認められていません。そのため、保険診療と自費診療の併用を希望する場合は、双方の治療が全額負担となってしまうことに留意する必要があります。
併用したくても全額自費となってしまうため、経済的に余裕のある人しか受けられなくなり、医療格差を生む可能性もあります。ただし、先進医療実施施設の認定を受けているクリニックであれば、併用できる先進医療があります。にしたんARTクリニックはすべての院が認定を受けているので、先進医療をお考えの際はぜひご相談ください。
にしたんARTクリニックの先進医療については、こちらのページをご覧ください。
不妊治療における先進医療
地方自治体独自の不妊治療の助成金制度も活用可能
不妊治療の保険適用以外にも、地方自治体が独自で設けている不妊治療専用の助成金制度もあります。これは、保険診療で行った体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)と併せて実施した先進医療にかかる費用に一部助成されるものです。ここでいう不妊治療における「先進医療」とは、2025年2月1日時点で先進医療として告示されている12の技術に限られており、保険適用と同じように43歳までという年齢制限や、3回ないし6回という回数制限もあります。
しかし、この助成金を活用すると経済的負担をさらに軽減できるので、お住まいの自治体に助成金制度がないかどうか調べてみましょう。
例えば、東京都では、先進医療を受けてかかった費用の10分の7について、150,000円を上限に助成 されます。さらに、区市町村ごとに独自の助成制度を設けている自治体もあります。
また、にしたんARTクリニックが展開する、東京都、京都府、大阪市、兵庫県、福岡県なども助成制度が設けられています。(2025年5月現在)。
保険適用の不妊治療を知って早めに不妊治療を始めよう
不妊治療の保険適用の範囲が広がったおかげで、不妊治療へのハードルが下がりました。今まで不妊治療にかかる費用が高額なために子供を持つことをあきらめていたカップルも、不妊治療に挑戦しやすくなったと考えられます。ただし、すべての不妊治療が保険適用となったわけではないので、保険適用の範囲がどこまでなのか、正しい知識を得るようにしましょう。
にしたんARTクリニックでは、不妊治療を検討されている方に無料のカウンセリングを行っています。保険適用の範囲を踏まえながら、患者さまファーストの目線に立った不妊治療の料金プランをご提案します。保険適用の範囲がどこまでなのかを知りたい場合も、カウンセラーにお尋ねください。
にしたんARTクリニックでの
治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。